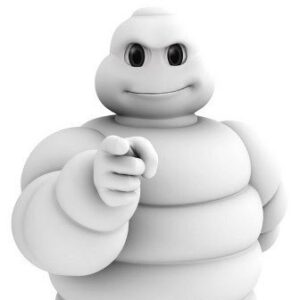悲しい思い出は枚挙に暇がないし、昔のことを思い出すなんて百害あって一利なしだと思ってきた。一生懸命忘れようとしてきた。
でも、夜寝る前とかふとした時に、いつの間にか脳裏に蘇ってくるシーンがあって。思い出す限り、列挙してみたいと思った。
幼稚園から小学校低学年まで
私は、父、母、姉がいる4人家族の末っ子で、常に姉と比べられていた。優秀で、親の言うことをよく聞く姉とは対照的に、出来損ない、我が強くて育てにくい子と呼ばれていた。しつけと称して日常的に母から暴力を受けていた。おちゃらけた道化師的な立ち回りが私のポジションだった。
いつも家では、母から蹴られたり、顔を引っ掻かれたりしていた。食べるのが遅いとかの理由だった気がするが、正直、理由は全く思い出せなくて、暴力を受けたことだけ覚えている。暴力の内容は、蹴とばす、顔を叩く、顔を引っ掻く、髪の毛を掴んで引っ張るなどで、頻度は週2、3回くらいだったのだろうか。当時、単身赴任をしていた父はいつも不在で、母、姉、私で過ごしていた。父は、週末に帰ってくると、決まって新しい引っ掻き傷を顔に作った私を見つけた。そんな時、父は母をなじるわけでもなく、私を見て「またネコに引っかかれたの」と笑った。
よく、下着1枚で家の外に出されて、夜まで玄関の前に座っていた。そんな時は家のドアを叩いて、泣きながら、入れてと叫んだ。繰り返されるその光景を、近所の人がまたかと言う顔で見ていた。父が入れてくれる時もあれば、見かねた近所の人が一緒に玄関ベルを鳴らしてくれることもあった。
何かで怒られた時に、父に夜中に抱っこされて家から近所の公園に連れていかれて、そこに置き去りにされたこともある。公園に行く道すがら、自分は捨てられるという意識があり、泣きながら「どこに行くの?パパの会社?」ときいた。父は会社員ではなかったが、その当時、大人はみんな会社にいくものだと思っていた。抱っこされて移動しながら、ヘンゼルとグレーテルではないが、引っ越したばかりの町の地図を、懸命に覚えようとしていた。結局、その公園から自力で家に帰った。
別の時に怒られたあとには、母にスーパーに置き去りにされた。当時、姉がバイオリンを習っていたが、レッスンの間、私と母は近所のスーパーの絵本コーナーで時間をつぶすのが常だった。その時母の機嫌がとても悪いのをわかっていたので、私は本に没頭するふりをしていた。そしたら、私は本当に本に夢中になってしまい、読みおわって気がついたら母がいなかった。泣きながら、スーパーの出口に向かっていたら、店員さんが「どうしたの?迷子?店内放送してあげるから、そこにいて」と言ってくれた。でも私には、母がもうスーパーにいないことがわかっていたので、その声を無視して外に出た。バイオリン教室に行く道を走り、信号を3つくらい越えたあたりで、先を歩いて行く母を見つけた。母に飛びついたら、母は拒まなかった。蛇足だが、その時から、私は本を面白いと思った。
ある時は、夕食を食べるのが遅いと言う理由で、夕食抜きになり、私はお風呂に入るために脱衣所にいた。そこに母は、冬みかんを1つ持ってきて、「これ食べな!」と私に投げつけた。私がそのみかんを拾って、皮を剥いていると、その動作が遅かったのか、母はそのみかんを再び私から取り上げ「こうやって食べるんだよ!」と叫ぶなり、みかんを丸ごと自分の口に入れた。かと思うと、そのみかんを口から吐き出し、私に「食べな!」投げた。私は、その母の唾液でぬるぬるしたみかんを精一杯急いで口に押し込んだ。お風呂場の扉を1枚挟んで、風呂場にいた父は、黙ってその騒動を聞いていた。
父と母の喧嘩は、日常茶飯事だった。単身赴任をしていた父が、週末に帰ってくると、週末の夜は決まって夫婦喧嘩があった。リビングルームや夫婦の寝室で繰り広げられていたその喧嘩を、私と姉は子供部屋から廊下に出て聞いていた。母の甲高い金切り声は比較的聞き取りやすく、喧嘩のトピックがわかったこともあった。父の低い声は、あまり何を言ってるかわからなかった。物が飛び交う音もしたし、ドシン、バタンと言うよくわからない音もした。何時間も続くその喧嘩は、父か母のどちらかが部屋を飛び出してくることで終わり、われわれ子どもは、喧嘩が終わりそうだと察すると素早く子供部屋に戻って寝たふりをした。
暴力を振るう母と無関心な父とは違い、祖父母は、いつも私に優しかった。母方の祖父母の家に遊びに行った時に、祖母から冗談めかして「このままこの家の子になるかい」と言われた私は、願ったり叶ったりだと思った。「そうする。1回お家に帰ってランドセルをとってきて、秋からこっちの小学校に通う」と私が答えると、祖母は困惑した顔をして、母と目配せをし合い、二度とその話題を出さなかった。
父方の祖父母の家は、福島の田舎にあったが、そこに夏に遊びに行った思い出は、いつも私の中で救われる良いものだった。だが、私が小学校低学年の頃に、嫁姑問題に苦しんでいた母が父方の親戚ともめたことをきっかけに、家族は福島に帰省しなくなった。その後のある日、私が父方の祖母(母にとっては姑)と電話で話していたことを母に見つかり、その時から私は母にとっては裏切り者になった。母にとって、姑は敵そのもので、その敵と話すなんて、私もスパイだ、この家の子ではないということだった。母が私を「お前は福島に似ている」となじる時、それは、「祖母のようにずる賢くて、要領良く人を騙す、性格が悪い、救いようがない奴だ」と言う意味であった。私の家庭内でのこうした評価は、現在まで変わらず定着している。
母はよく姉妹を比べた。正確には、姉を猫かわいがりして私を嫌った。母にとって姉は、どんなに失敗しても可愛い子であり、要領が悪いところがあっても素朴で純朴な良い子であった。私はいつまでも裏切り者であり、勉強で姉を追い抜くようになっても、要領が良く、ずるがしこい子だから性格は悪いのだと言われ続けた。
母は、しょっちゅう自分がこの家を出て行くと言って子供を脅かした。実際に、何度か家出をした。母が「出て行くから」と叫ぶたびに、私は泣く演技をしたが、心の中では早く出ていけばいいのにと思った。そして、母が出ていった後は実際は、父や姉と平和に過ごしていたのだ。
(続く)