特段お腹も空いていないのに、夜にぽっかり空いた時間を楽しく過ごさないと、と思って、ワインを開けてつまみとともに胃に流し込む。
1日中家で仕事をして、食べることしか楽しみがないので、仕事がひと段落して気分転換が欲しいとき、体が欲してもいないのに、ついつい台所に来て何かを口に入れてしまう。
今の食べ物が10年後の自分を作るなんて恐ろしいことだ。アイスクリームとせんべいとワインでぶよぶよのミシュランマンみたいなのが生まれたらどうしよう。
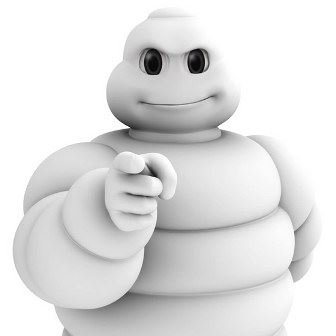
★ ★ ★
そだったのは、食育にこだわりのある家だった。母親は、「生活クラブ」という生協を信奉していて、そこの豚肉を食べれば病気にならないと信じていた。
「生協の良い食べ物を食べさせてあげた。そんなことしてあげられる家は多くない。健康にいられるのは親のおかげなので、感謝しろ。」
と常日頃から感謝を要求していた親は、私に子供が生まれたときも「子供には生活クラブ生協の食べ物をあげること」と指示をした。そんなわたしの小さいころの食事には、いくつか思い出がある。
★ ★ ★
母は、子供に暴力をふるう人だった。わたしへの暴力のきっかけは些細なことで、大抵は単に母の機嫌が悪いだけだった。当時はこれは躾であり、自分が悪いと思っていた。
父はそんな母のことを「またヒステリーを起こしているの」とぼやきながら、止めたことはなかった。わたしがほっぺたに母から引っ掻かれた傷をつけていても「また猫にひっかかれたの」と笑っていた。
4、5歳の頃のこと、食べるのが遅いという理由で、夕食を取り上げられたわたしは、お風呂に入ろうと脱衣所にいた。そこに母が脱衣所へ来て怒鳴った。
「お前、また食べないで済ませようというのか」
黙っていると、母は「ほら、これ食べな!」と1個の冬みかんを投げつけた。これが夕食代わりのようだった。食べろといわれたものは食べないといけない。私は、冬みかんをひろって皮をむいた。フサを割ろうとした瞬間、母は、のろのろしているわたしにしびれをきらしたのか、手からみかんを取り上げ、
「こうやって食べんだよ!」
と叫ぶなり、みかんを丸ごと自分の口に押し込んだ。母の口いっぱいに、冬みかんがはまり込んだ。
あ、母が自分で食べるのか。
そう思いながらぼーっと見ていると、母は口いっぱいにほおばったみかんを吐き出して、私に投げつけた。
「食べな!」
吐き出されたみかんは、脱衣所の床をコロコロ転がり、角で止まった。私は、母の唾液にまみれてぬるぬるし、床のホコリがついたみかんを拾い、急いで口いっぱいに放り込んだ。母は私の前で仁王立ちでなり、扉一枚を隔てた浴室でこの騒動を聞いている父は沈黙していた。
★ ★ ★
大人になってから、数えきれないほど幸せな食事をした。友人、恋人、新しい家族と。横浜や銀座で毎日のように飲み歩いていた時は、先輩にたくさんおごってもらい、おいしいものを食べた。
そんな中で、からだに良い食事というのは、単に生協のオーガニックな食べ物を食べることではなくて、もちろん名店のフルコースを食べることでもなくて、楽しいとか幸せな、ポジティブな気持ちでその食卓を囲めることだと気づいた。
そういう幸せな食卓を囲み続けられれば、10年後の自分の体もこころも健康になると言い聞かせながら、ばかうけと白ワインを飲む夜である。







